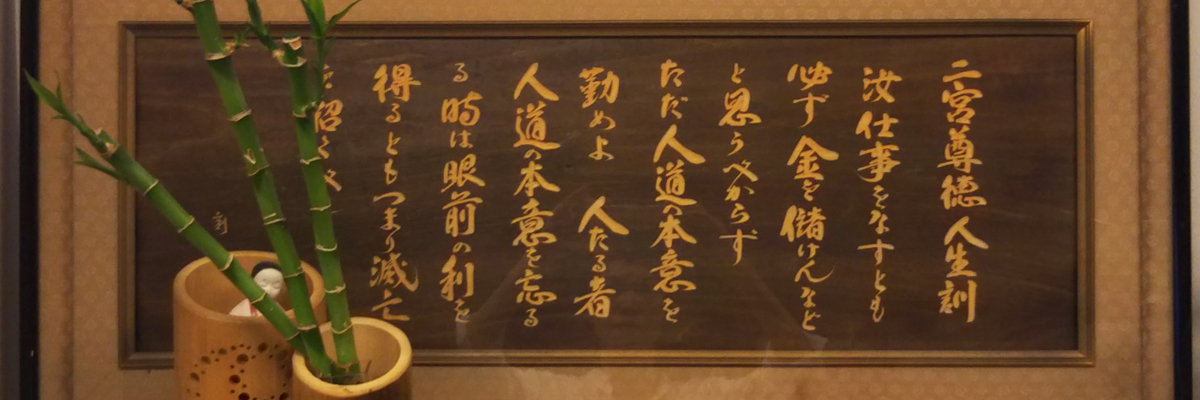春と秋、年に2回お彼岸があり、春の彼岸は「春分の日」を中日として前後の3日を合わせた7日間ということですから、今日はちょうど彼岸入りですね。
「暑さ寒さも彼岸まで」とは言ったものですが、こちら福岡は週末あたりからだいぶ冷え込んでいます・・・^^;
そんな彼岸にはお墓参りに行く風習がありますが、仏教では生死の海を渡って到達する悟りの世界を「彼岸」といい、その反対側の私達がいる世界を「此岸(しがん)」といい、
彼岸は西に、此岸は東にあるとされており、太陽が真東から昇って真西に沈む春分と秋分は、彼岸と此岸がもっとも通じやすくなると考え、先祖供養をするようになったといいます。

彼岸のお墓参りは仏教的な意味を持つならわしですが、彼岸はインドなど他の仏教国にはない日本独自のものだといい、起源には諸説ありますが「彼岸」は「日願」でもあるため、日本古来の太陽信仰や祖霊信仰が結びついたという説も。
農耕民族の日本人は古くから、春には豊穣を祈り、秋には収穫を感謝し、作物を作るときに欠かせない太陽や自然、自分たちを守ってくれる先祖の霊に感謝してお供えをする「日願(ひがん)」という習わしがあり、これに仏教の「彼岸」の考え方が融合する形で、「お彼岸」の行事になったということです。
このような理由もあってか、神道でも、お彼岸にはご先祖様への感謝を伝える意味でお墓参りをするようですね。
私自身、数年前まで「彼岸っていつ? 何?」という感覚でしたし、春分の日などの祝日に対しても「お休み嬉しい!」という感覚が先行し、その日の意味や趣旨などさほど意識をすることもありませんでしたが、カグヤで働き「子どもの未来」を考えるうちに、先人たちが繋いでくれたもの、残してくれたものに自然と目が向くようになりました。
そして、彼岸を含めこんな風に歴史や背景を知りながら、様々な行事やお米づくりの経験を年々繰り返すほどに、暮らしの中で少しずつ馴染んできて、知識というよりは感覚としても理解しやすくなっていくのを感じます。
人生や暮らしにおいて何を大切にするかはそれぞれだと思いますが、選択肢のひとつとして子どもたちに残していけるよう、季節の巡りと共に、自然やご先祖様との繋がりを感じやすい暮らしを繋いでいけたらと思います。
かぐやかコーディネーター
宮前 奈々子